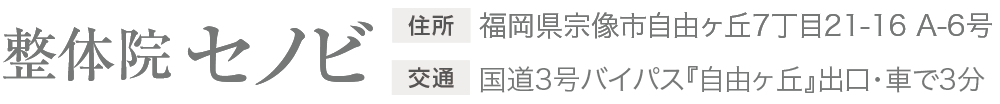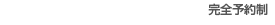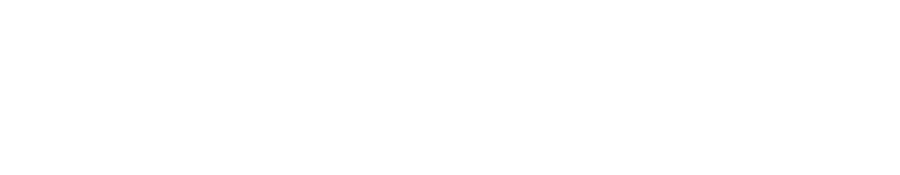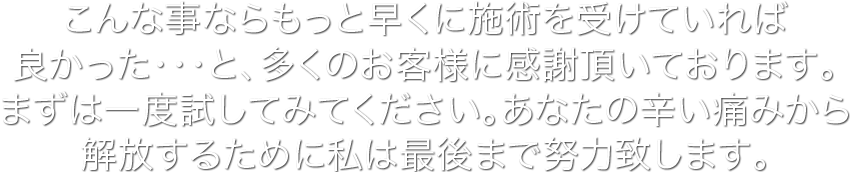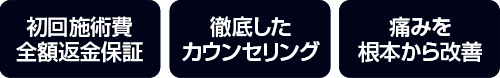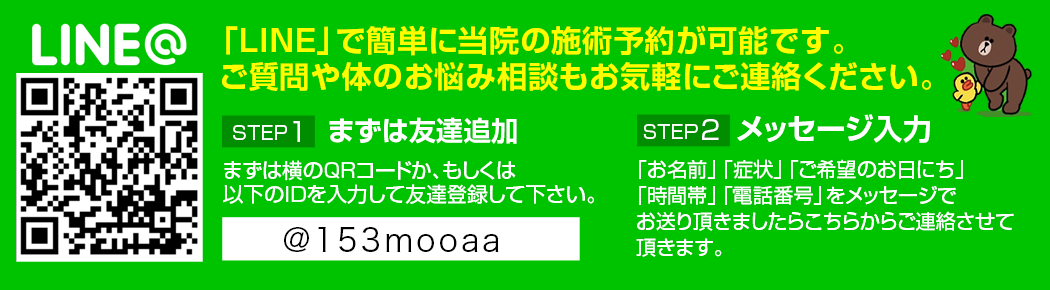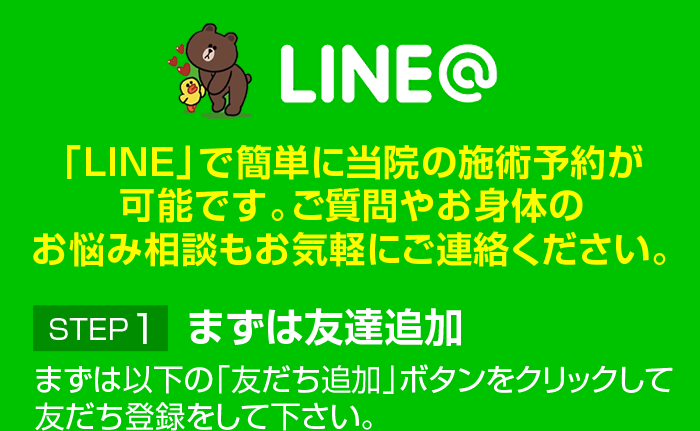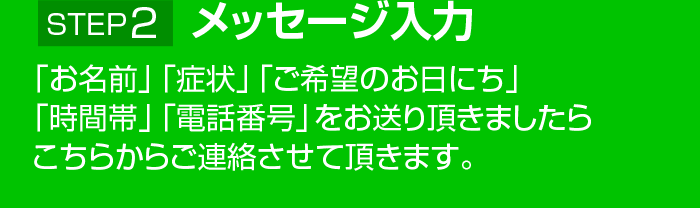長時間の運転で疲れないための体の使い方

車を運転するとき、長時間の運転が続くと肩こりや腰痛
足のむくみなど、さまざまな体の不調が現れることがあります。
特に、姿勢が崩れたまま運転を続けると、疲労が蓄積しやすくなります。
姿勢を整えて過ごすことは名医の治療に匹敵するほど
『腰痛から解放される』手段になります。
そこで今回は、整体師の視点から
長時間の運転でも疲れにくい体の使い方を解説します。
1. 運転時の疲れの原因
長時間運転による疲れの主な原因は、以下のようなものが挙げられます。
① 姿勢の崩れ
長時間同じ姿勢を続けることで、骨盤が歪み、猫背や反り腰を引き起こします。
その結果、腰や背中に負担がかかり、疲れやすくなります。

② 筋肉の緊張
アクセルやブレーキを踏むことで、脚の筋肉が常に緊張状態になります。
また、ハンドルを握り続けることで、肩や腕の筋肉にも負担がかかります。
トラック運転手はクラッチ操作で股関節が硬くなっているケースもあります。

③ 血行不良
長時間座り続けると、下半身の血流が滞りやすくなります。
特に足のむくみや冷えを感じる人は、血流の悪化が原因になっています。

2. 疲れにくい運転姿勢
疲れにくい運転をするためには、正しい姿勢を意識することが大切です。
① シートの位置を調整する
- シートの高さ:目線が適切な高さになるよう調整。
- 背もたれの角度:100〜110度の角度が理想的。
- シートの前後位置:ブレーキを踏んだときに膝が軽く曲がる位置。

② ハンドルの持ち方を意識する
ハンドルを強く握りすぎると、肩や腕が疲れやすくなります。
軽く握ることで、リラックスした状態を保ちましょう。
片手で操作する方はバランスよく左右の手を使うようにしてください。

3. 長時間運転で疲れにくい方法
① こまめに休憩を取る
1時間ごとに1分でもよいので体を動かしてください。
休憩を取ってストレッチができれば完璧です!
疲労を感じる筋肉に対してストレッチをすれば良いです。

② 深い呼吸を意識する
緊張すると呼吸が浅くなり、肩こりの原因になります。
深呼吸を意識して、リラックスした状態を保ちましょう。
③ 骨盤を意識する
骨盤を立てるように座れたら完璧です!
これは腰痛予防の7割を占めるくらい重要なので
必ず意識してください!

4. 運転前後にできるケア
運転前後のケアをすることで、疲労を最小限に抑えることができます。
① 骨盤運動
骨盤の前・後傾を繰り返し行います。
骨盤の前傾を強調して行ってください(上図)。
お腹の筋肉が伸びるようにお腹を突き出す
ことがポイントです!

② 運転後のケア
運転後は、腰や足のストレッチをして血流を促しましょう。
特に、太ももやふくらはぎを伸ばすと効果的です。

5. まとめ
✅ 正しい姿勢を意識してシートを調整する
✅ ハンドルをリラックスして握る
✅ こまめに休憩を取り、ストレッチをする
✅ 深呼吸をしてリラックスする
✅ 運転前後にストレッチを取り入れる
Posted: 3月 1st, 2025 under 腰痛予防.
Comments: none